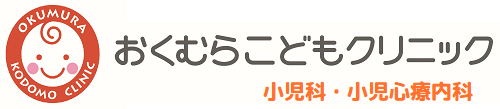おひさま 第104号~麻疹/乳幼児期のスマホ利用について~
おくむら先生のお話【麻疹】

最近麻疹ウイルスに感染した方の報告があいついでいます。ほとんどは海外で感染し、発症している成人例ですが、中にはワクチンを接種する前の1歳未満の乳児の感染の報告もあります。私が医者になりたての頃は日本でも普通に麻疹の患者さんがみえました。10年ほどたつと、子供に対するワクチン接種が進み、2回の定期接種になると、麻疹の患者さんは激減して、輸入感染症として扱われるようになりました。
麻疹は麻疹ウイルスに感染することによって発症します。通常でも症状はかなりつらいのですが、重症化することもあります。特効薬はなく、対症療法(症状をやわらげる治療)のみで、なおるまで我慢するしかありません。麻疹ウイルスに感染すると7〜21日の潜伏期間をへて、発症します。感染力は非常に強く、集団の中で一人の発症があれば免疫のない人は必ずうつります。すれ違っただけでうつると思ってもいいくらいです。麻疹の患者さん一人で12〜18人の免疫のない人に感染させます。海外への往来が活発な現在、いつ麻疹に感染している人と接触しても不思議ではありません。症状は38度以上の高熱、咳嗽、鼻汁、結膜炎(目の充血、眼脂)で始まり、口の中の頬粘膜に白い斑点(koplik斑)が出現します。一旦解熱したのち再び発熱して、全身に発疹が出現します。この発疹はしばらくの間色素沈着が残ります。通常7〜10日間程度で徐々に回復していきます。肺炎、脳炎、中耳炎などの合併症を起こすことがあり、重症肺炎や急性脳炎では命に関わることもあります。特に乳幼児、免疫不全などの基礎疾患のあるお子様、妊婦さんは重症になりやすいです。また麻疹にかかって数年の無症状の期間を経て発症する、亜急性硬化性全脳炎(SSPE)を合併することがあります。麻疹にかかった方の数万人に一人が発症する病気で、最初学校の成績低下、記憶力の低下、いつもと違った行動、感情不安といった精神的な症状や、歩行が下手になった、持っているものを落とす、字が下手になった、体ががくんとなる発作(失立発作)が起こるなどの症状できづかれ、発症後数ヶ月から数年の経過で徐々に神経症状が悪化し、数年から十数年で意識消失、寝たきりとなり、死に至ります。麻疹にかかると、それだけでも大変なうえに、時には重症化して死に至ることもあります。急性期を脱しても数年後に死に至る合併症を発症することもあります。麻疹に特効薬はありません。
かからないようにするにはワクチンしかありません。定期接種の対象のお子様はもちろんのこと、それ以外でも、麻疹にかかったことがなく、ワクチンも接種していない方は接種をお勧めします。
麻疹は麻疹ウイルスに感染することによって発症します。通常でも症状はかなりつらいのですが、重症化することもあります。特効薬はなく、対症療法(症状をやわらげる治療)のみで、なおるまで我慢するしかありません。麻疹ウイルスに感染すると7〜21日の潜伏期間をへて、発症します。感染力は非常に強く、集団の中で一人の発症があれば免疫のない人は必ずうつります。すれ違っただけでうつると思ってもいいくらいです。麻疹の患者さん一人で12〜18人の免疫のない人に感染させます。海外への往来が活発な現在、いつ麻疹に感染している人と接触しても不思議ではありません。症状は38度以上の高熱、咳嗽、鼻汁、結膜炎(目の充血、眼脂)で始まり、口の中の頬粘膜に白い斑点(koplik斑)が出現します。一旦解熱したのち再び発熱して、全身に発疹が出現します。この発疹はしばらくの間色素沈着が残ります。通常7〜10日間程度で徐々に回復していきます。肺炎、脳炎、中耳炎などの合併症を起こすことがあり、重症肺炎や急性脳炎では命に関わることもあります。特に乳幼児、免疫不全などの基礎疾患のあるお子様、妊婦さんは重症になりやすいです。また麻疹にかかって数年の無症状の期間を経て発症する、亜急性硬化性全脳炎(SSPE)を合併することがあります。麻疹にかかった方の数万人に一人が発症する病気で、最初学校の成績低下、記憶力の低下、いつもと違った行動、感情不安といった精神的な症状や、歩行が下手になった、持っているものを落とす、字が下手になった、体ががくんとなる発作(失立発作)が起こるなどの症状できづかれ、発症後数ヶ月から数年の経過で徐々に神経症状が悪化し、数年から十数年で意識消失、寝たきりとなり、死に至ります。麻疹にかかると、それだけでも大変なうえに、時には重症化して死に至ることもあります。急性期を脱しても数年後に死に至る合併症を発症することもあります。麻疹に特効薬はありません。
かからないようにするにはワクチンしかありません。定期接種の対象のお子様はもちろんのこと、それ以外でも、麻疹にかかったことがなく、ワクチンも接種していない方は接種をお勧めします。
スタッフコラム【乳幼児期のスマホ利用について】

スマホはいろんな動画やアプリがたくさんあり、子育てにも便利なアプリもあります。
子どもが公共の場などでぐずったり、泣いたりした時に一時的に使用するのは良いと思います。しかし、便利だからといって、常にスマホで子守をさせることは悪影響となる可能性があります。例えば、親も子どももスマホやタブレットを長時間使用していると、大切な親子の会話や体験が奪われてしまいます。また親がスマホに夢中だと、赤ちゃんへの関心が無視され安全面でも配慮できなくなります。
また幼児になると、スマホをせがんで取りあげると泣いて暴れるなどスマホ依存になることも・・・
子どもが公共の場などでぐずったり、泣いたりした時に一時的に使用するのは良いと思います。しかし、便利だからといって、常にスマホで子守をさせることは悪影響となる可能性があります。例えば、親も子どももスマホやタブレットを長時間使用していると、大切な親子の会話や体験が奪われてしまいます。また親がスマホに夢中だと、赤ちゃんへの関心が無視され安全面でも配慮できなくなります。
また幼児になると、スマホをせがんで取りあげると泣いて暴れるなどスマホ依存になることも・・・
スマホの影響

長時間の使用で言葉の遅れや目の発達に影響します。乳幼児の成長では人とのやり取りで言葉を覚え、近くや遠くをみることで眼球の動きが発達します。一人で小さな画面を見続けることは成長の妨げになります。
乳幼児期は視力が発達する重要な時期で、日本の子どもの視力はゲーム機などの普及で悪化しています。また子どもの運動機能や体力も外遊びなどで体を動かして育ちますが、体を使った遊びが減り、運動不足による肥満などの生活習慣病が問題視されています。また、夜間のスマホ使用は強い光で体内時計の発達を乱し、睡眠パターンを崩しやすくなります。
乳幼児期は視力が発達する重要な時期で、日本の子どもの視力はゲーム機などの普及で悪化しています。また子どもの運動機能や体力も外遊びなどで体を動かして育ちますが、体を使った遊びが減り、運動不足による肥満などの生活習慣病が問題視されています。また、夜間のスマホ使用は強い光で体内時計の発達を乱し、睡眠パターンを崩しやすくなります。
親子の時間を大切に

言葉を話せない赤ちゃんは、泣いたりぐずったりして「おなかがすいた」「オムツがぬれた」などの生理的欲求や「抱っこして」「あそんで」などの情緒的欲求を訴えます。なぜ泣くのかわからないときには、声掛けや抱っこをすることで親子の絆が出来ていきます。授乳中は、メディアなどは消し、目を合わせてゆったりとした気分で赤ちゃんと向き合いましょう。声を出した時は声かけをして相手してあげましょう。ことばが話せない赤ちゃんにも、積極的に話しかけることが言葉の発達には大切なことです。親子で散歩や外遊びをしたり、本を読み聞かせたり、同じものに向き合って過ごす時間を作りましょう。自分の気持ちに共感してもらうという体験は自己肯定感を育て、心の発達の基礎となります。
現代生活の中でスマホは欠かせないツールで、正しい使い方をすればとても便利なものです。
親や子どもに関わる大人が乳幼児からきちんとルール作りをして、子どもがスマホと上手に付き合えるような環境作りをしておくことが大事です。
※日本小児科医会参照
親や子どもに関わる大人が乳幼児からきちんとルール作りをして、子どもがスマホと上手に付き合えるような環境作りをしておくことが大事です。
※日本小児科医会参照