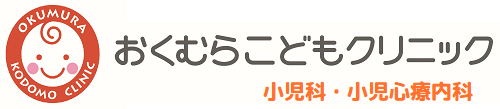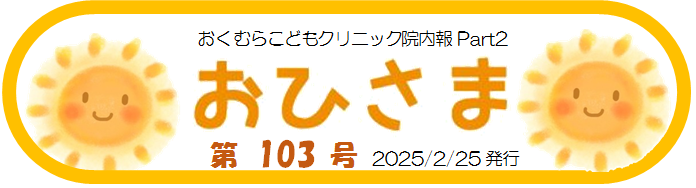おひさま 第103号~愛着(アタッチメント)/嘔吐や下痢のときの水分のとりかた~
かさい先生のお話【愛着(アタッチメント)】

子育てでの重要性が認知されてきたことに、愛着(アタッチメント)があります。発達とこころの外来をしていてもここに問題があるお子さんも多く、愛着の問題があると親御さんの変化もないと中々よい方向に進んでいかないなあと常日頃思い悩むことが多いです。愛着はイギリスの精神科医ボウルビィによって提唱された「愛着理論」で、子どものこころの土台となる「安全基地」と呼ばれるものです。
発達とこころの外来で愛着が気になる親御さんには、わかりやすく次の様に説明しています。「お子さんのこころの中にニコッと笑ったお母さん像をしっかり造ってあげて下さい」と。
生まれてすぐ、母子は一体化しています。そして子どもは少しずつ親と離れて遊ぶようになります。子どもは少し離れて遊んでいると時に不安になってきます。振り向いてお母さんの顔を見てお母さんがにっこり微笑むと、お子さんはまた安心して一人で遊べます。少しずつお母さん像がこころの中にできてくると、距離が離れても安心して遊ぶことが出来ます。最終的にお子さんのこころの中にお母さん像がしっかりできるとお母さんがいなくても、こころにお母さんがいるので頑張って一人で活動することが出来ます。このような状態が「安定愛着」と言われるものです。
発達とこころの外来で愛着が気になる親御さんには、わかりやすく次の様に説明しています。「お子さんのこころの中にニコッと笑ったお母さん像をしっかり造ってあげて下さい」と。
生まれてすぐ、母子は一体化しています。そして子どもは少しずつ親と離れて遊ぶようになります。子どもは少し離れて遊んでいると時に不安になってきます。振り向いてお母さんの顔を見てお母さんがにっこり微笑むと、お子さんはまた安心して一人で遊べます。少しずつお母さん像がこころの中にできてくると、距離が離れても安心して遊ぶことが出来ます。最終的にお子さんのこころの中にお母さん像がしっかりできるとお母さんがいなくても、こころにお母さんがいるので頑張って一人で活動することが出来ます。このような状態が「安定愛着」と言われるものです。

一方、愛着関係、お母さん像がうまく形成されないと、「不安定愛着」と言われ、成長してからの人格形成に影響してくるといわれます。愛着に問題があるとはじめに目につくのは、保育園や幼稚園の時に見られる母児分離不安です。確かに愛着に問題のないお子さんでも始め親と離れることを嫌がりますが、愛着に問題があると極端に程度が強く、期間も長くなります。園の先生方はそのうち慣れるといって無理矢理分離をさせますが、無理に分離させるのではなく愛着の視点にも気を遣って欲しいと思います。また外来をしていると低学年の不登校も愛着面に問題があるお子さんが多いと感じます。おそらくこころのお母さん像が薄いので、集団生活の場面で一人でやっていかなければならない負担が大きくなり、不安が強くなりやすいのでしょう。
母と子の間で安定した愛着が形成されるには、抱っこや授乳などのスキンシップとともに、子どもに対して、表情やしぐさ、声に素早く反応し満たしてあげることが子どものこころの成長や愛着形成に大切だと考えます。
母と子の間で安定した愛着が形成されるには、抱っこや授乳などのスキンシップとともに、子どもに対して、表情やしぐさ、声に素早く反応し満たしてあげることが子どものこころの成長や愛着形成に大切だと考えます。
スタッフコラム【嘔吐や下痢のときの水分のとりかた】

ここ1か月、嘔吐や下痢で受診されるお子様が増えているように感じます。
このような時に気をつけたいのが、脱水症状です。
水分のとり方のコツを覚えておくと、防ぐことができます。
このような時に気をつけたいのが、脱水症状です。
水分のとり方のコツを覚えておくと、防ぐことができます。
脱水症状になるとどうなるの?
人の体のエネルギー源のメインは糖です。糖は体の中にある程度ストックされていますが、お子様の場合、ストックが少ないので、糖分が摂取できないとすぐに使い果たされてしまいます。糖分が足りなくなると、体はエネルギー源として、脂肪を燃やします。脂肪を燃やすと、ケトン体という代謝産物ができます。このケトン体が、腹痛、嘔吐などの原因になります。さらに、血糖値が下がると、ぐったりし、意識混濁などの低血糖の症状がでて、低血糖が続くと脳にダメージを与えてしまうこともあります。
何を飲んだらいいの?
塩分と糖分のバランスが整っていて、吸収が早く、効率よく水分摂取できるのが、経口補水液(OS-1)ですが、糖分よりも塩分が多く含まれているため、飲みにくいと言われがちです。最近では、リンゴ風味やゼリータイプのものもあり、塩味が感じられにくいため、試してみてください。また、ドリンクを一口サイズの製氷皿で凍らせて食べる方法もあります。それでも嫌がって難しい場合は、リンゴジュースやスポーツ飲料で糖分、うどんのおつゆやお味噌汁の上澄みなどで塩分をとりましょう。
飲ませ方のコツ
まずは5cc(ペットボトルのキャップ1杯程度)を5分おきに与えてください。嘔吐が治まってきたら、与える間隔を5分→3分→1分と縮めていきます。途中で嘔吐しても、全部が出ているわけではないので、飲ませるのを止めずに少量ずつ続けましょう。
何を食べたらいいの?
吐いているうちは、食事をとっても吐いてしまうので、ある程度水分がとれるようになってから、消化の良い食べ物から進めましょう。
おかゆ・うどん・軟らかく煮た野菜スープ・バナナ・リンゴ・ゼリー・プリンなど。
おかゆ・うどん・軟らかく煮た野菜スープ・バナナ・リンゴ・ゼリー・プリンなど。
いつ登園・登校したらいいの?
嘔吐や下痢が治まって、普段の食事がとれるようになれば可能です。
どんな時に受診したらいいの?
水分をとることができない・嘔吐が続いている・尿が半日以上でない・血便が出た・ぐったりしている などの症状がある場合。